ニューロダイバーシティから考える、多様性のこれから | 武田薬品

すべての働く人の特性が輝く社会ってナンダ?
ニューロダイバーシティから考える、多様性のこれから
index
- ニューロダイバーシティを通じて患者さんへ寄り添う
- すべての従業員の強みを活かすマインドセットの重要性
- 特性のグラデーションを理解し、企業として更に強く
- 100人100通りの特性を尊重できる社会がゴール
- すべての人が働きやすい会社を目指して
脳や神経における特性の違いを多様性と捉え、相互に尊重する概念「ニューロダイバーシティ」。タケダは、それらの特性を活かしながら誰もが社会の中で活躍し、生き生きと暮らしていくことの実現を目指している。2022年10月には、その思いに賛同した日本橋の多くの企業・団体とともに「日本橋ニューロダイバーシティプロジェクト※」を発足。ニューロダイバーシティという新しい概念の理解促進と、その考え方を社会に広げるための情報発信を大きな目的として活動を行っている。
今回は、同プロジェクトの企画運営を担うジャパンファーマビジネスユニットの森威さんに、ニューロダイバーシティにまつわる現状と課題、プロジェクトを通して叶えたい未来について伺った。
「日本橋ニューロダイバーシティプロジェクト」公式サイトはこちら
ニューロダイバーシティを通じて患者さんへ寄り添う
― 森さんが「日本橋ニューロダイバーシティプロジェクト」に携わることになった経緯を教えていただけますか?
製薬会社として医薬品を通じて社会に貢献することはタケダのミッションの一つですが、その中でも患者さんを一番に考える企業文化が強く根付いており、私自身も常に意識している点です。
私は神経領域の中でも特に発達障害領域を担当していることから、医薬品による貢献以外にも当事者の方々のためにもっとできることはないかと模索していました。例えば生活環境など、本当に困っていることへの支援方法を考える中で、いちばんフィットした考え方が「ニューロダイバーシティ」でした。
一般の方々や企業にこの考え方を広く認知していただくことで、当事者の方々が少しでもより自分らしく暮らすことに貢献できるのではないかと考えたことがきっかけです。
すべての従業員の強みを活かすマインドセットの重要性
― ニューロダイバース人材※が社会で働くためには、当事者と受け入れる企業の双方の理解が重要だと思いますが、どのような意識の変革が必要だと考えていらっしゃいますか?
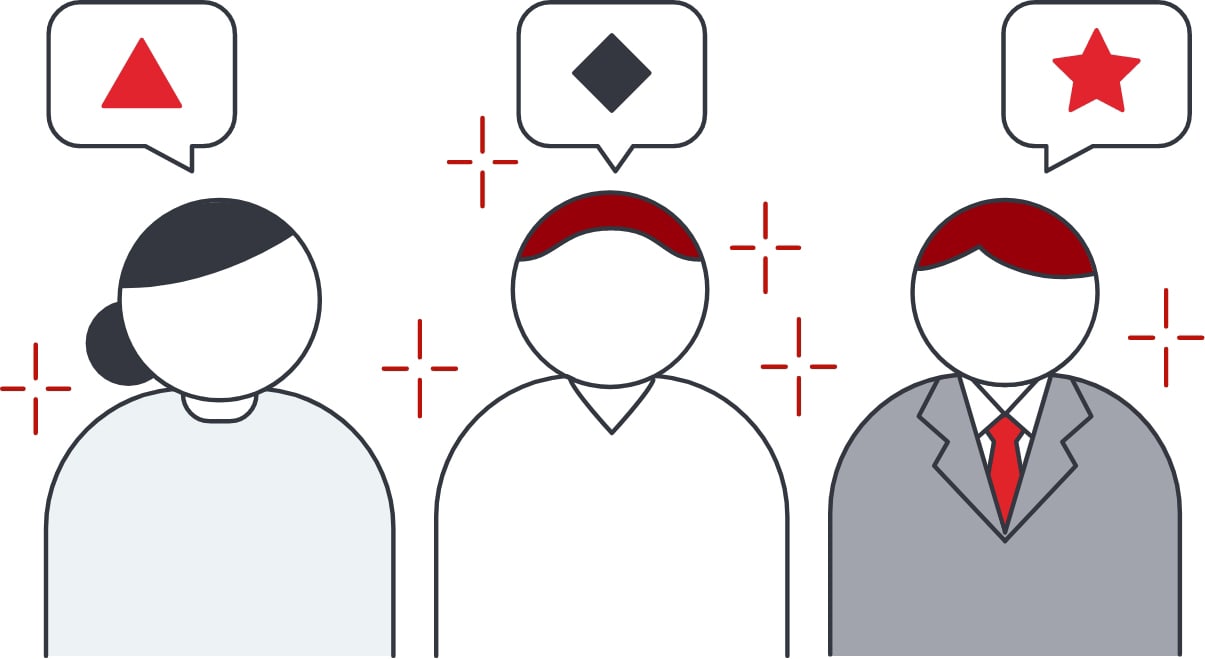
強みとなる特性にフォーカスするためには、当事者が「私はこれが得意です。これは苦手です。」と明確に伝えることができる環境があり、それを周囲やマネジメント側が受けとめられるマインドセットがまずは重要です。
タケダのブラジル拠点では、2022年からニューロダイバース人材の採用を行っています。それが実現しているのは、上司や周囲の方々が当事者の特性を理解したうえで働きやすい環境をつくっている結果でもあると考えています。
※自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)、ディスレクシア(発達性読み書き障害)など、神経発達の多様性を持つ人材のこと。特性のグラデーションを理解し、企業として更に強く
― ニューロダイバース人材を受け入れ、協働していくためには、まずはお互いを理解し、受け入れるための素地を作っていくことが大切ということですね。

― これまでお聞きしたような考え方が浸透し、ニューロダイバース人材の採用が当たり前のことになった際に、企業側にはどのようなメリットがあるとお考えですか?
ニューロダイバース人材がそれぞれの特性を活かして働けることは、企業全体のパフォーマンス向上に繋がると考えています。将来的に活躍の場が広がるメリットの一つとして、昨今問題となっている労働人口減少の対策にも貢献できるかもしれないですね。
100人100通りの特性を尊重できる社会がゴール
― 「ニューロダイバーシティ」に関する森さんのご意見をお伺いしてきましたが、森さんが考えるこの活動のゴールを教えてください。
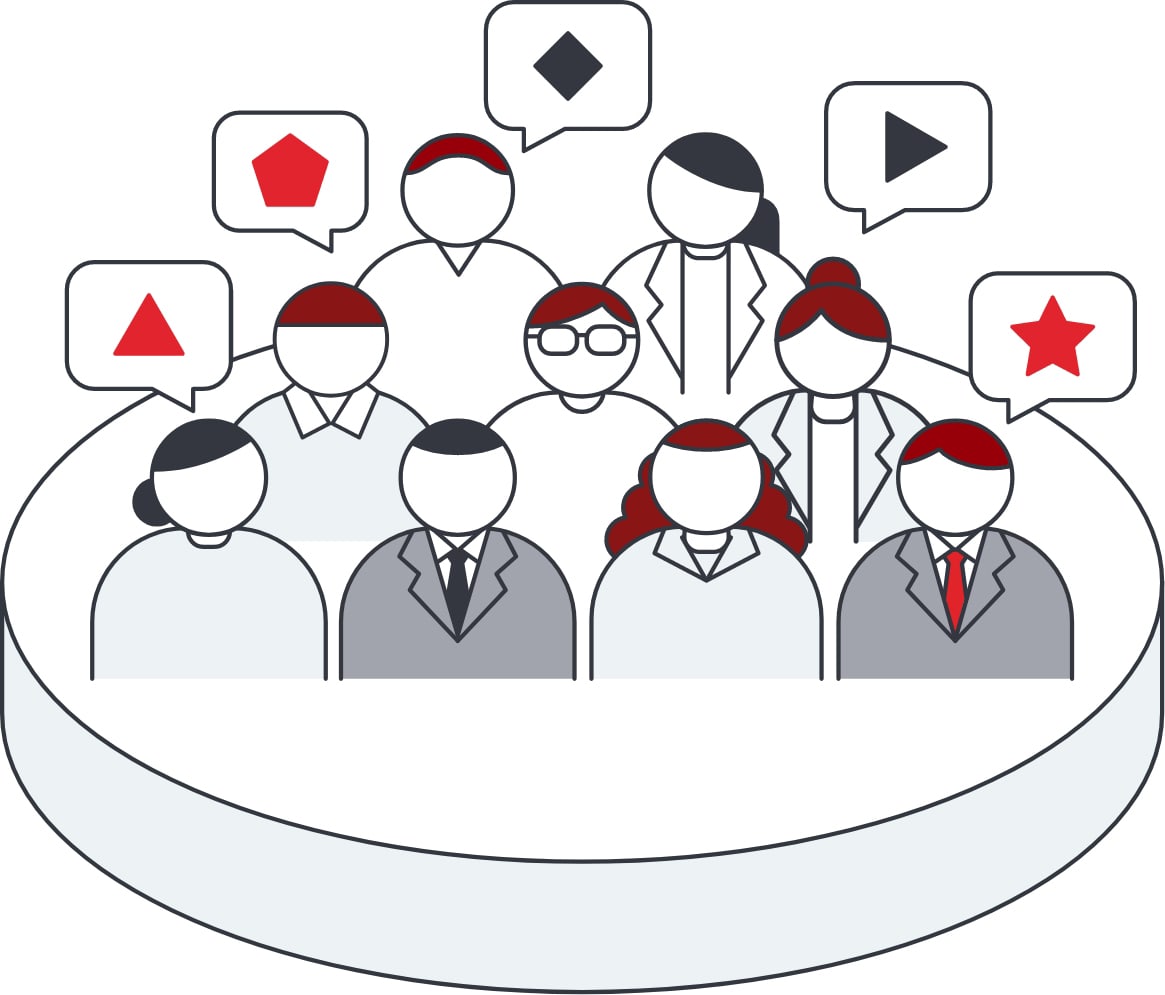
そのためにまずは、「日本橋ニューロダイバーシティプロジェクト」の活動を多くの企業に知っていただき、この考え方をすべての企業が取り入れていただくきっかけになると、とてもありがたいです。
すべての人が働きやすい会社を目指して
― 森さんのお話から、「ニューロダイバーシティ」の浸透に向けた熱い想いが伝わってきました。そのモチベーションの源泉について教えてください。
プロジェクトを立ち上げる以前に、ニューロダイバース人材の方とお話しする機会があり、皆さんが苦労されていることを知りました。翻って自分のことを考えた時に、タケダでは私が働きやすいように上司や周りの従業員のサポートが常にあり、すごく恵まれている環境だと感じました。
以前から従業員が働きやすい環境の提供に取り組んできたことはタケダの強みです。そこへさらに「ニューロダイバーシティ」の考え方を浸透させることができれば、もっとみんなが働きやすくて強い会社になれるかもしれない。いや、強くなってほしいという想いが自分の根底にはあり、それがモチベーションになっています。
― 最後に、タケダが現在行っている取り組みや今後の展望について教えてください。
現在タケダでは、学生を招いた体験プログラムや、従業員を対象としたニューロダイバース人材の理解を深めるためのセミナーを行っています。社内にニューロダイバース人材への、より深いマインドセットが浸透したその先に、タケダの「ニューロダイバーシティ」の実現があると信じて今後も取り組んでいきたいと考えています。
Profile

森 威
ジャパンファーマビジネスユニット医療政策・ペイシェントアクセス統括部患者・疾患啓発所属。神経領域、特に発達障害領域を担当していることから、2022年「日本橋ニューロダイバーシティプロジェクト」の立ち上げから携わり、企画運営を担当。発足と同時にWebサイトや冊子の制作を行い、2023年4月からは賛同企業・団体と協力しながら定期的にワークショップを開催するなど、さまざまな啓発活動を展開中。




